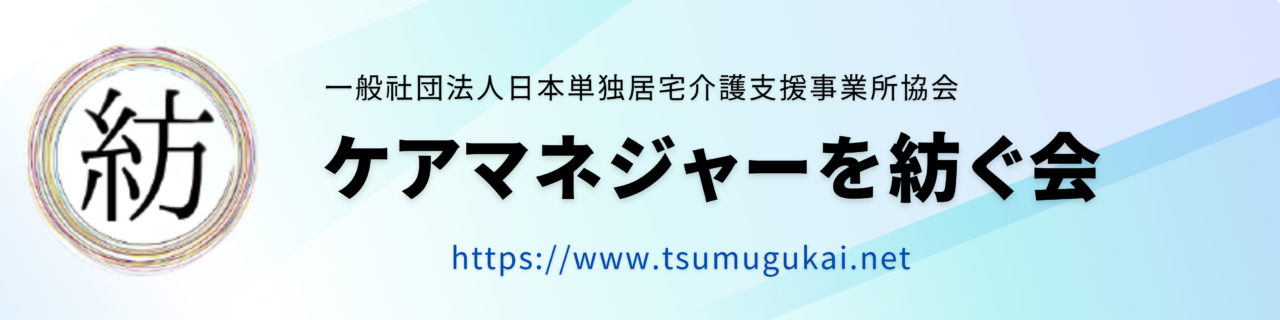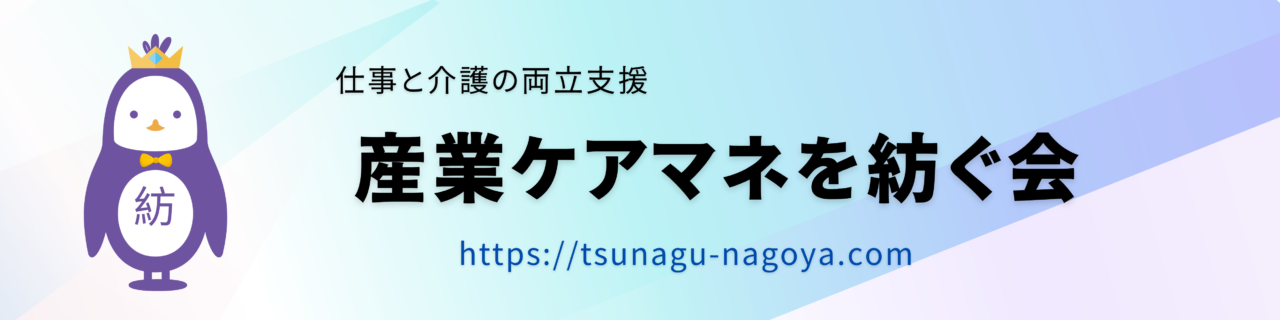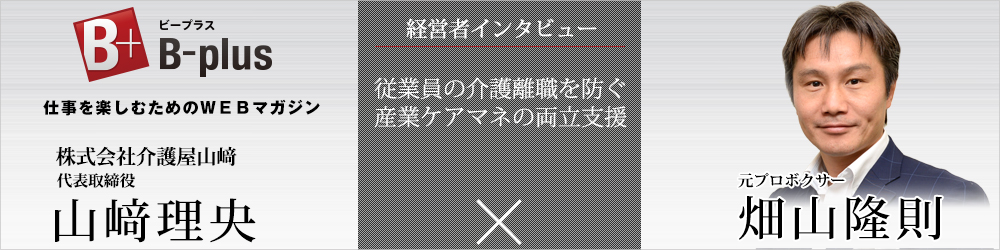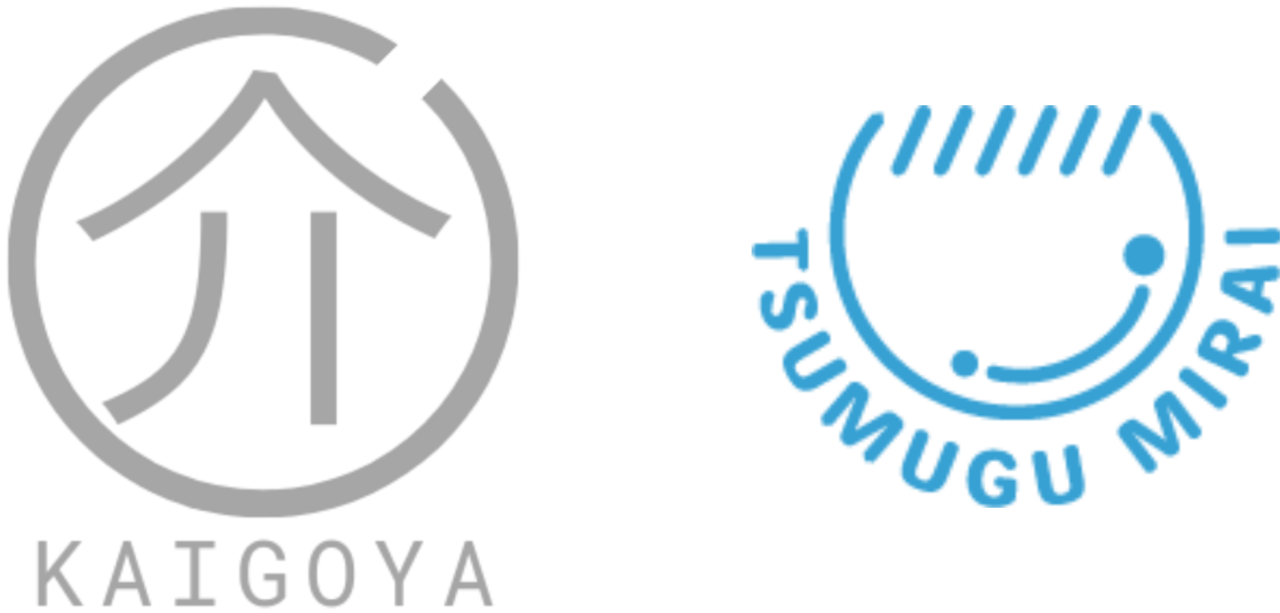みなさん、おはようございます。
奈良市を中心にケアマネジャー・産業ケアマネをしています
山﨑です。
介護支援専門員(ケアマネジャー)として、日々ご自宅を訪問して感じることは、利用者や家族が「困った」と声を上げたときには、すでに事態が進行しているケースが多いことを日々実感しています。

「言えない」には理由がある
- 利用者(=家族)は、迷惑をかけたくないという遠慮
- 「相談するほどのことじゃないと思っていた」
- 「もう少し自分で頑張れると思っていた」
こうした思いから、“限界ギリギリ”まで声を上げないことが、特に介護者には多く見られます。
会社でも同じです。
働く介護者は、「上司や同僚に迷惑をかけたくない」「介護を理由に評価が下がるのでは」と考え、悩みや限界を抱え込んだまま働き続けてしまうのです。

🧭 ケアマネとして現場で学んだこと
- トラブルは“相談されてから”ではなく、“相談されないこと”から始まる
- 定期的な訪問や面談で、“何でもない会話”の中に支援のヒントがある
- 「元気そうに見えても、支援が必要なことがある」と常に意識する
つまり、「言ってくれたら対応する」では支援としては遅いというのが、ケアマネとしての実感です。
💼 企業にもあてはまる視点
産業ケアマネとして企業と関わる中でも、
この「予防的支援の発想」が非常に重要だと感じます。
- 「声を上げてもいい雰囲気」
- 「声を上げなくても、こちらから気づける仕組み」
- 「“ちょっとした違和感”を放置しない文化」
これらを企業文化の中に根づかせていくことが、
結果的に離職防止・メンタル不調予防・組織の持続力向上につながるのです。

まとめ:ケアマネの視点が企業の支援にも活かせる
「何かあったら言ってね」ではなく、
「何もないうちに、話しませんか?」
この一言こそが、仕事も介護も、両立支援の第一歩です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日もどうぞ、素敵な一日になりますように!